
変易と不易⑦ 〜糟糠の妻〜
私自身の体験談になりますが、30歳から35歳の頃、必死に仕事に邁進しても上手く進まない、結果が出ないということが何年も続いておりました。

周りでは、その時々で景気の良い話もちらほら聞いており、なぜ自分には結果が伴わないのか、自分は神に見放されているのではないか、その頃の私は神を信じても居ないのに、上手くいかないことを、そう考えて拗ねていることもありました。

そう腐っていた理由のひとつに、景気の良さそうな歳の近い経営者を見ると、能力で比較すれば、どう考えても私の方が優れているのに何故、という思いが湧いていたと記憶しております。
相手の仕事ぶりも詳しく知りもしないのに、そう思うのは傲慢でありますが、24歳から未熟なりに歩合営業職を自営で続けて来た私は、その頃もう自営歴10年目であり、成功哲学であるとか、営業能力であるとか一通り身に付け、それなりの個人能力が高まってはおりました。

が、その実状は、数人の社員を最低雇用金額で、なんとか雇っているだけで、潰れていないだけの、ほぼ自転車操業のような状態であったものですから、30代も半ばに差し掛かった男としての自分が、ついて来てくれる社員達の不安そうな視線を浴びながら、経営者としてあまりに不甲斐なく、毎日が苦しいやら情けないやらの怨念めいた心持ちで日々を過ごしておったものでございます。
私には、苦楽を共にした糟糠の妻がおりますが、この妻が当時の頃、あまりに重苦しい雰囲気を纏っている私を見かねて、1泊2日の旅行に連れ出してくれまして、私はお金が掛かることは極力控えておりましたから、今は旅行など行く時ではないと言いましたが、こんな時だからこそ気分を変えなくてはいけない、と言ってくれるもので、渋々着いて行ったことがありました。
【糟糠の妻】
糟糠とは、酒粕と米糠、つまり貧しい暮らしを意味します。貧しい時代から共に苦労を重ねてきた妻のこと。

中国後漢の時代、光武帝の重臣である宋弘が光武帝の姉の再婚相手に選ばれそうになった際、「貧しいときの知己を忘れてはならない、糟糠の妻を家から追い出してはならない」と述べたことから、この言葉は、貧しい時代から連れ添った妻を大切にするという故事からきています。

行き先は京都でして、何やら腕に数珠(パワーストーン)を付けるのに、見えないものが見える人がおる有名な店で、何とか予約が取れたから行くそうで、私はほぼ付き添いといったことでした。

その頃の私は、やはり詳しく知るわけでもないのに、神や仏にアレルギーがあり、見えないものを語る人が詐欺師にしか思えなかったものですから、店の隅の椅子に座り、俯(うつむ)いた状態で、いつもと変わらず会社の行く末を不安に思っていたところ、突然、彼女(今の妻)が私を呼びに来まして、何事かと私が問いましたら、どうやら店の店主が、私がとても悪い運気を纏っており、このままでは、その内に命も腐って危ういと思うので、ほっとけないと言うとるのだそうです。
私はそれを聞いて、心から余計なお世話だと思いましたが、散歩中に嫌がる犬を引き摺るかの如く、彼女に店主の前まで連れて行かれまして、仕方なく私は店主に挨拶をしたのでございます。
「どうも、私に何か御用ですか?」
すると店主は、
私を宥めるような、憐れむような、また包み込むような笑みを浮かべて、こう言ったのです。
「惜しいねぇ。貴方には人気がある、才能もある、全て上手く行くはずなのに、全く思い通りに行かない。そう思って苦しんでいるのではないですか?」
私は、それを聞いて大きく動揺したのを、今でも思い出します。


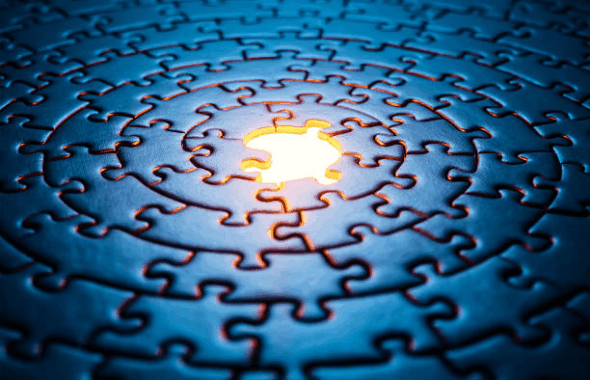
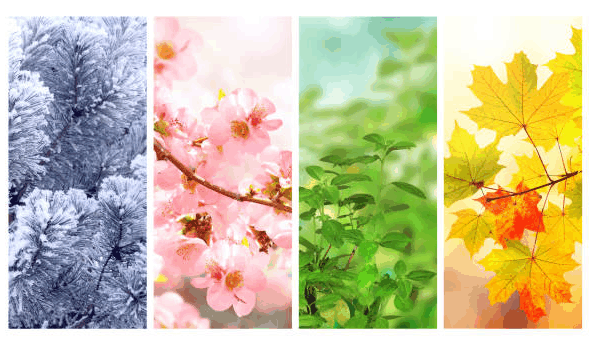
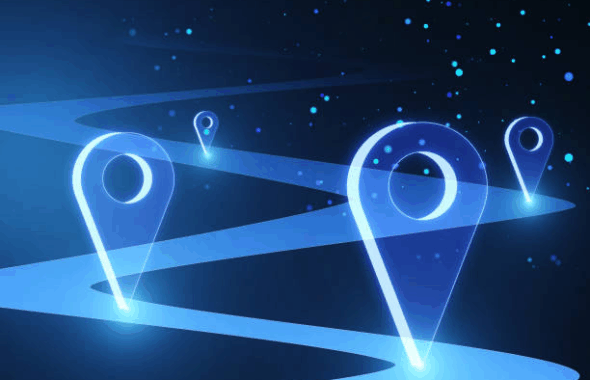
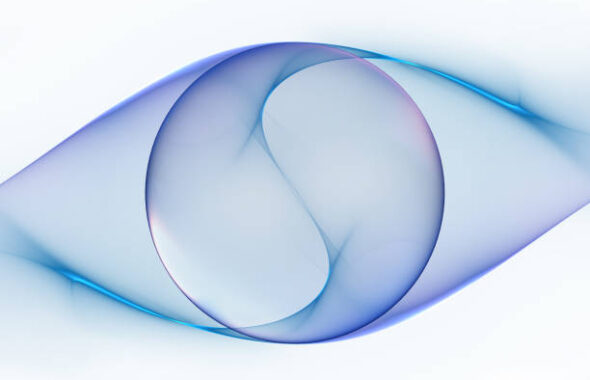


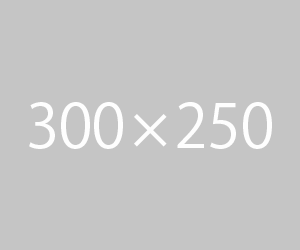
この記事へのコメントはありません。